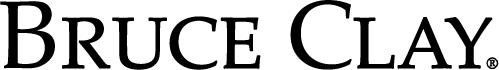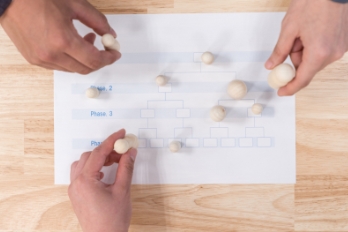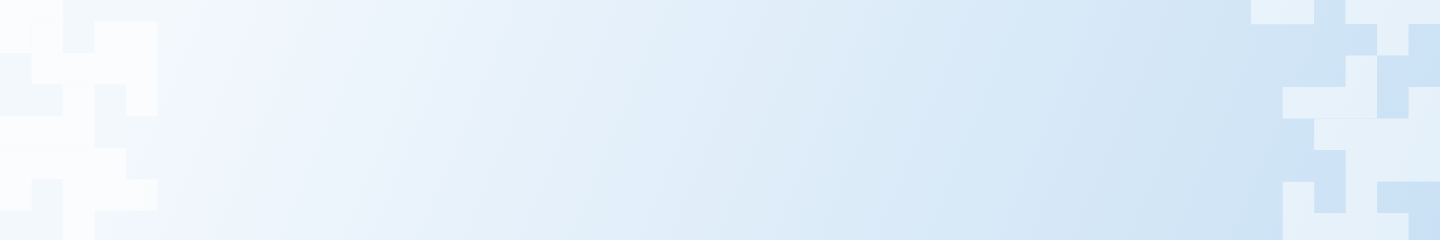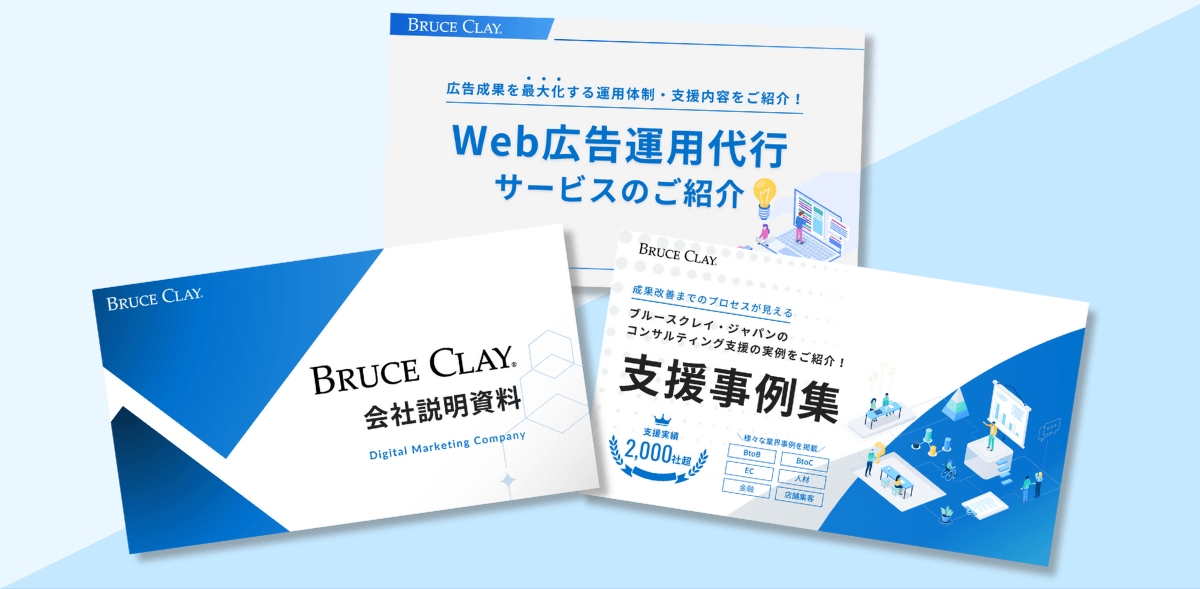2025.07.10 2025.07.10

「AIでなんとかなるんでしょ?」に感じる違和感
「最近はAIがあるから、広告運用もほとんど自動で進むんですよね?」
そんな声を耳にする機会が増えました。
ChatGPTをはじめとする生成AIや、Google広告のP-MAXキャンペーンのような自動化された配信手法の登場により、広告運用が「人の手を離れていくもの」と考える人が増えているように感じます。
たしかに、AIは配信の最適化やクリエイティブ生成など、多くの作業を効率化してくれます。
業務の省力化という点では、間違いなく大きな進歩です。
しかし一方で、「自動化が進みすぎて中身が見えない」「成果の要因を説明できない」といった声も、現場では少なくありません。
結局のところ、AIを活かせるかどうかは、人間の”問い方”と”判断力”にかかっています。
本記事では、“人が手放すべきでない運用領域”について整理してみたいと思います。
目次
なぜ「AI任せ」だけでは成果が出ないのか?
未来予測はAIだけでは不十分
AIはあくまで、過去のデータに基づいて“最適解”を導く存在です。
確かに、広告配信においても過去の傾向をもとにした配信先の最適化やクリエイティブのパターン選定といった処理は非常に優秀で、精度も高いと感じる場面は多いでしょう。
ですが、マーケットは常に変化しています。
競合の動き、消費者心理、季節性や市場全体の空気や流れ、そうした“データには表れにくい変化”に対し、AIが柔軟に対応できるとは限りません。
過去に最適化されたロジックは、未来の打ち手にはなりません。
その微妙なズレに気づき、修正できるのは、現場を見ている人間の経験です
数値では測れない“伝わる”という感覚
AIは、クリック率やCVRなどの指標を最適化し、数字上は“良い結果”を出すことができます。
しかし、それが本当にターゲットの心に届いているかどうかは、また別の話です。
たとえば同じCPAであっても、「誰に」「どんなシーンで」「どう受け取られたか」によって、事業成果への貢献度はまったく変わってきます。広告の成果は、コンバージョン率やクリック率といった“数字”だけでは語れません。
「これ、ちゃんと伝わっているのか?」
その問いに答えられるのは、商品やユーザー、文脈を理解している人間の肌感覚です。
「数字がいい=成果が出ている」とは限らない
AIは、クリック率やCVRなどの指標を最適化し、数字上は“良い結果”を出すことができます。
しかし、その数値が「本当に意味のある成果」なのかは、もう一歩深く見る必要があります。
たとえば同じCPAでも、獲得後のLTVや解約率、成約率に差が出ることはよくあります。そのため、広告数値だけでなく、商談データやユーザーインタビューなど、定量・定性の情報を組み合わせて判断する視点が求められます。
広告指標の数字だけを見て「うまくいっている」と思っても、売上などの実際のビジネス成果に結びついていなければ意味がありません。そのギャップに気づき、必要な情報を取りにいけるのは、商品や顧客の背景を理解しているマーケターだからこそだと思います。

AIは、思考の余白をつくる“道具”である
バナーやコピーの生成、入札の自動最適化。
以前は人が時間をかけていた作業を、いまAIがスピーディに肩代わりしてくれるようになりました。
確かに、AIを使えば手は空きます。
でも本当に大事なのは、その空いた時間で「何を考えるか」。
ただ任せきりにするのではなく、人間が“判断”と“戦略”に集中できる状態をつくることこそ、AIの価値です。
つまりAIは、“すべてを任せる存在”ではなく、“考えるために使いこなす道具”なのだと思います。
生成AI時代に広告運用担当者が絶対に手放せない3領域
誰に・何を・どう届けるか。その設計はAIには任せられない
AIは、過去のデータや一般的なセオリーをもとに配信設計の提案をしてくれます。
けれど、その通りに運用すれば成果が出るほど、広告は単純ではありません。
競合や市場の状況、ターゲットの変化、商品特性やブランドの方向性。
加えて、各広告媒体の特性や自社の予算・リソース──それらを総合的に踏まえて、配信設計を組み立てていくのは、広告運用者の仕事です。
つまり「誰に」「何を」「どう届けるか」。
その設計図を描けるのは、現場を理解し、マーケティングの全体像と広告運用の接点を捉えられる人間だけだと感じます。
「いい感じ」で進めない。クリエイティブ判断の嗅覚
このコピーで本当にいいのか?このクリエイティブは、ターゲットに刺さるのか?
そうした問いを、“都度立ち止まって考える力”が、長期的に成果の差を生むと思っています。
なぜなら、成果が良くとも「なぜ効いたのか」がわからなければ、次に活かせないからです。
広告のパフォーマンスは、ちょっとした言い回しや色味の違いで大きく変わります。
にもかかわらず、“なんとなく良さそう”な案がそのまま採用されてしまう場面も、少なくありません。
AIが提案してくるコピーやバナー案が、便利であることは間違いありません。
けれど、「これで本当に伝わるのか?」と自ら問い直し、必要があれば修正し、磨いていく。
その判断力は、日々の運用と経験の中でしか育たないものです。
運用者として、こうした感覚に意識を向けられるかどうかが、結果の質に影響すると感じています。
A/Bテストの結果を“再現可能な知見”に変える力
A/Bテストは、単なる勝ち負けの確認ではありません。
CVRの高かった案の背後には、必ず「なぜ」があります。
その背景を読み解き、「なぜこの訴求が刺さったのか?」を把握することで、初めて次の打ち手に活かせる“再現可能な知見”になります。
テスト結果の数値を見て終わるのではなく、次の一手に落とし込む視点と判断力こそが、運用担当者の力の見せどころです。
成果を出している企業に共通する、AIとの付き合い方
ここまで触れてきたように、AIには多くの強みがあります。
クリエイティブ案の生成や自動入札など、手数を増やす・作業を早める領域では、すでに十分“戦力”です。
ただ、それをどう活かすかは、やはり人の考え方次第です。
マーケティング戦略、KPI設計、文脈理解、判断の微調整──
そうした領域を“人が手放さないこと”が、成果を生み出す前提になっています。
成果を出している企業は、AIに期待しすぎることも、逆に構えすぎることもありません。
うまくいく組織には、共通して「人とAIの関係性を丁寧に設計している」という特徴があります。
- どこまでAIに任せるか
- どこを人が担うか
- どのフェーズで判断し、調整するか
AIと人の役割が曖昧なままでは、判断や打ち手に一貫性が持てず、成果も安定しにくくなります。
だからこそ、体制そのものを「AI前提」で設計できているかが問われるのです。
AIに運用を丸投げしている企業より、AIを徹底的に活かしながら、人の判断力を武器にしている企業の方が、やはり強いと感じています。

まとめ|あなたの運用は、AI時代に「強く」なっているか?
AIがあるから、もう人が考える必要はない。
そうした期待も一部では見られますが、広告運用の現場はまだそこまで単純ではありません。
成果を出している企業は、「任せる」のではなく、「どう使い、どう活かすか」を突き詰めています。
その差を生むのは、人間の問いの質や、判断力の深さです。
AIを活かせるかどうかは、使い手次第です。
運用が複雑化し、判断のスピードも求められるなか、思考を止めず、問いを投げかけ、判断を重ねる。その積み重ねが、AI時代の広告運用を“強く”していくのだと思います。

marke@bcj
ウェブマーケティングコンサルタント 詳細な分析から成果改善までをコミット!
BCJメールマガジンのご登録
最新のセミナー情報やお役立ち情報をメールにてお届け致します!
-

【2026年最新版】LLMO対策会社10選を徹底比較!費用やSEOとの違い・選び方も解説
2026.01.14
View more
-

【2026年のSEO展望】GEO・SOV時代の最適戦略とは?AI時代に勝ち続けるための全戦略とKPIシフト
2025.12.03
View more
-

AI Overviews(AIO)でSEOはどう変わる?クリック率への影響や今すぐ知っておきたい最新の対策方法
2025.11.06
View more
-

データと社員の声でひもとく、ブルースクレイ・ジャパンの“リアル”な魅力とクライアント成果を生む現場の在り方
2025.11.05
View more
-

AIとSEOの新時代「SEO 2.1」──AI時代のSEO戦略とは?検索エンジン最適化はどこへ向かう?AI対策についても紹介!
2025.10.28
View more
-
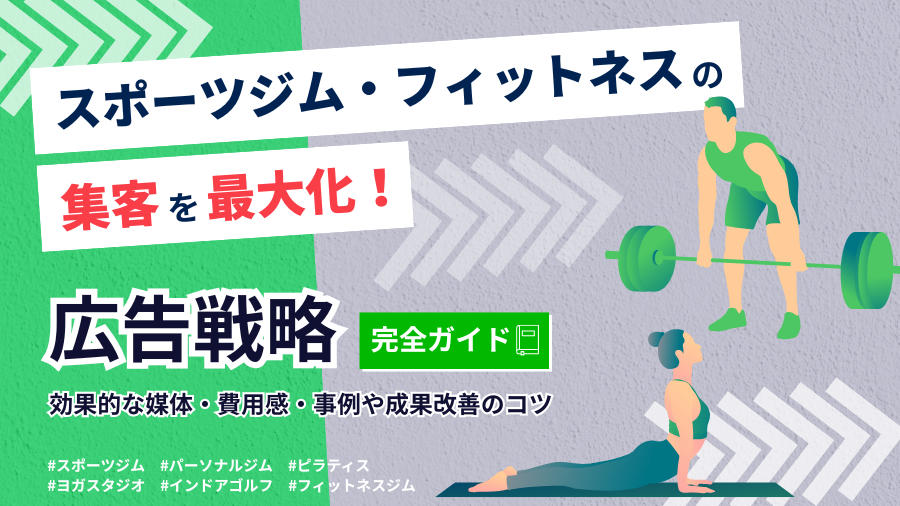
ジム・フィットネス業界の集客を最大化する広告戦略【完全ガイド】媒体・費用・代理店の選び方まで徹底解説
2025.10.09
View more