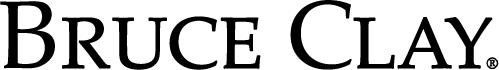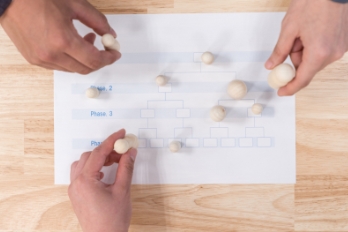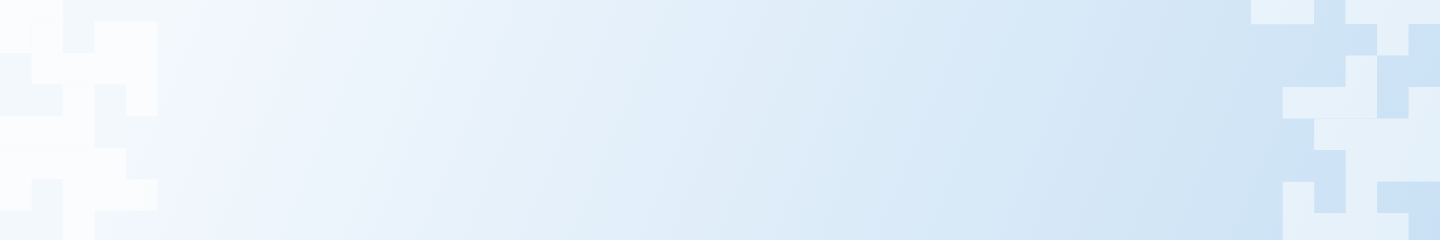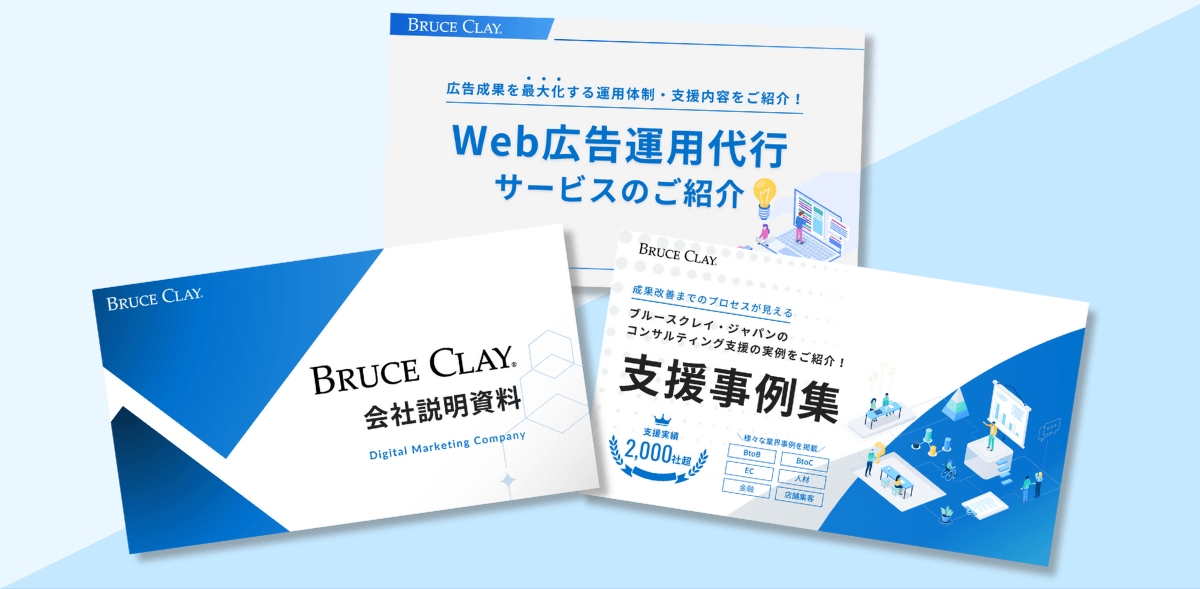2022.02.08 2018.08.13

Googleスマート自動入札機能がアップデート
2018年7月末にGoogleより、スマート自動入札機能についていくつかの更新が発表されました。
自動入札の中でも比較的利用者の多いと思われる目標広告費用対効果や全般的な機能についてまとめました。
1.目標広告費用対効果で特に重要なコンバージョンに集中
目標広告費用対効果について、アルゴリズムの変更が行われました。
内容としては、特に重要なコンバージョンに対する予測に使う要素が増えたようです。
具体的な例でGoogleは下のように伝えています。
たとえば、高額な買い物が夕方以降や週末に集中する傾向がある場合、更新版の「目標広告費用対効果」入札戦略では、夜間や週末に発生するオークションで入札単価が積極的に引き上げられ、それ以外では入札単価が抑制されて費用対効果の向上が図られます。
弊社では、ECサイトで平均売上単価の20倍する一部の高額な商品が売れてしまったため、自動入札が過学習を起してその商品ばかり獲得しようとするも、購入頻度が高くなかった商品であったため、配信ボリュームがシュリンクした事例があります。
便利な機能であると信じて導入後は自動化任せにするのではなく、やはり定期的な数値確認とチューニングをすることが大切です。
2.過去のCV数が少なくても最適化スピードがより短く
現在、目標コンバージョン単価(目標コンバージョン単価内でコンバージョン数を最大化する自動入札)を使用する際は、過去30日間に30以上のコンバージョンを獲得していることが推奨され、目標広告費用対効果では過去30日に50以上のコンバージョンを獲得していることが推奨されています。
今回のアップデートでは、コンバージョンデータが少なくても最適化スピードが上がったと発表があり、Googleヘルプでは成果向上する例として、以下のようなケースを挙げています。
特定のリマーケティング リストに登録されたユーザーによるコンバージョンが多い場合には、「目標コンバージョン単価」入札戦略で、そのリストの登録ユーザーにキャンペーンの予算を多く割り当てることができます。
コンバージョンやユーザーリストの定義は、表示回数やクリック数の定義のように全てのアカウントで画一的ではないため、このカスタムできる定義をいかにビジネスの拡大に繋がる設計にすることができるかが自動入札の成果の分かれ目の1つのポイントではないかと考えられます。
3.最後に
現在、広告運用の現場では手動入札から自動入札への過渡期のような状況にあるかと思われます。
その中で、自動入札のロジックにブラックボックスな部分があるから、改善や成功ナレッジが広まるまで手動入札を中心に運用をする。という考え方も一つの正解だと思います。
ただ、もう一つの考えとして、自動入札のロジックで開示されている方向性を理解しつつ、そこにカスタマイズ性(戦略的意図を組み込める部分)はどこなのかを考え、トライ&エラーを繰り返しながら、自動入札に身を寄せて一緒に変化していくことも、トレンドの波が目まぐるしく変わるウェブマーケティングの楽しみであり醍醐味ではないかと考えています。
BCJ管理人
ブルースクレイ・ジャパン(株)サイトの管理人です。 担当業務は全ファネル領域におけるサイト改善コンサルです。
BCJメールマガジンのご登録
最新のセミナー情報やお役立ち情報をメールにてお届け致します!
-
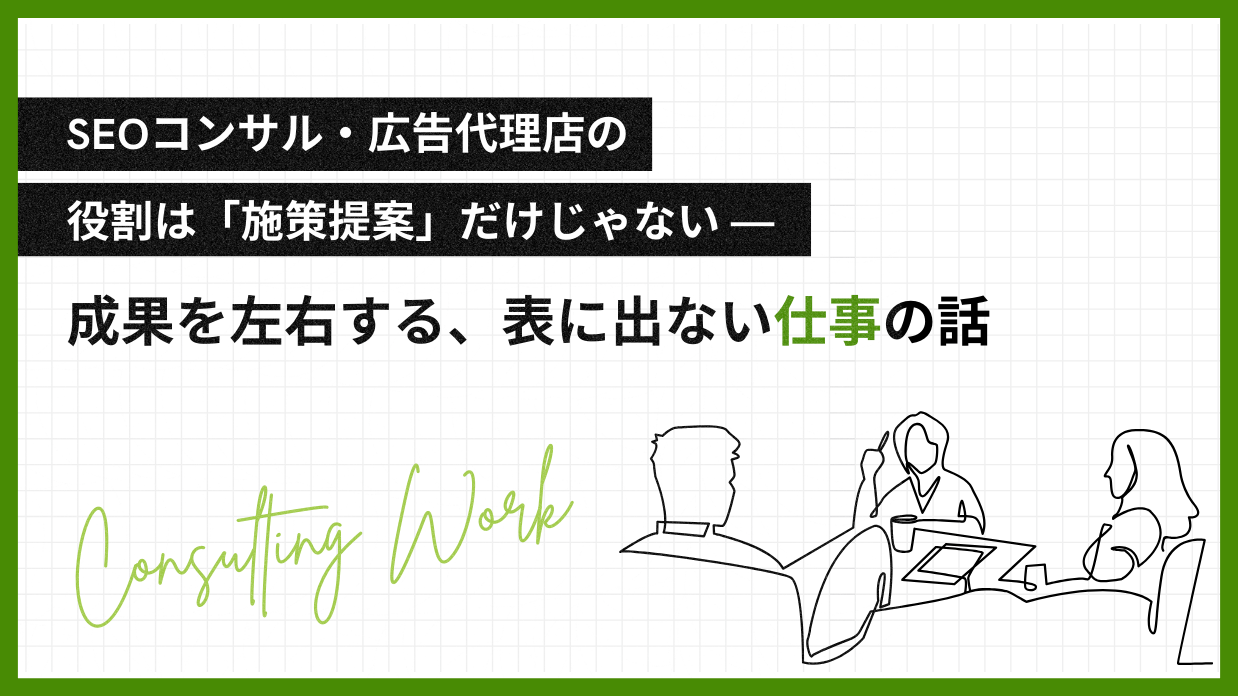
SEOコンサル・広告代理店の仕事内容は「施策」だけじゃない──成果を左右する、表に出ない仕事の話
2026.02.10
View more
-

【サイト改善事例】カテゴリ修正とタグ追加で、既存コラムの検索順位が改善した理由
2026.02.10
View more
-

Googleが自らのルールを破る時:Google for Developersの「SEOやらかし」を暴く!
2026.02.03
View more
-

【2026年最新版】LLMO対策会社10選を徹底比較!費用やSEOとの違い・選び方も解説
2026.01.14
View more
-

【2026年のSEO展望】GEO・SOV時代の最適戦略とは?AI時代に勝ち続けるための全戦略とKPIシフト
2025.12.03
View more
-

AI Overviews(AIO)でSEOはどう変わる?クリック率への影響や今すぐ知っておきたい最新の対策方法
2025.11.06
View more